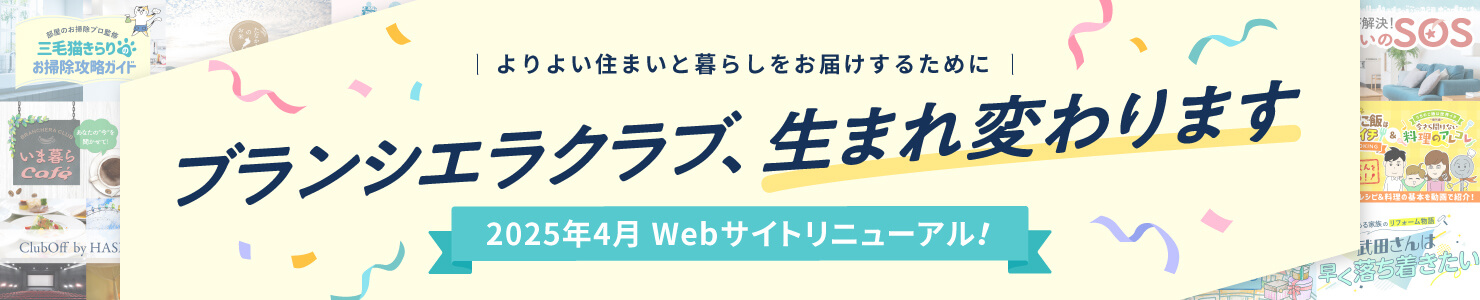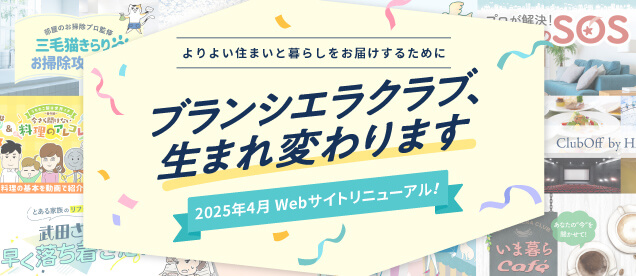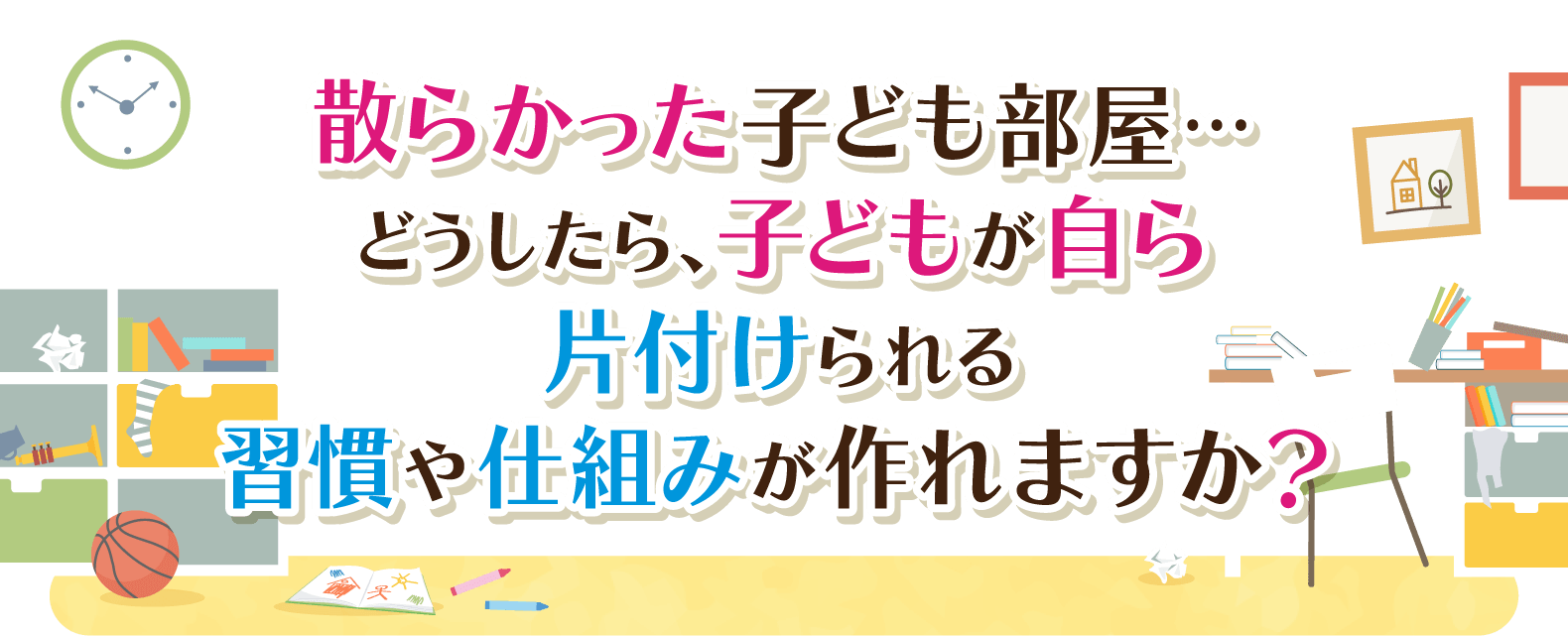
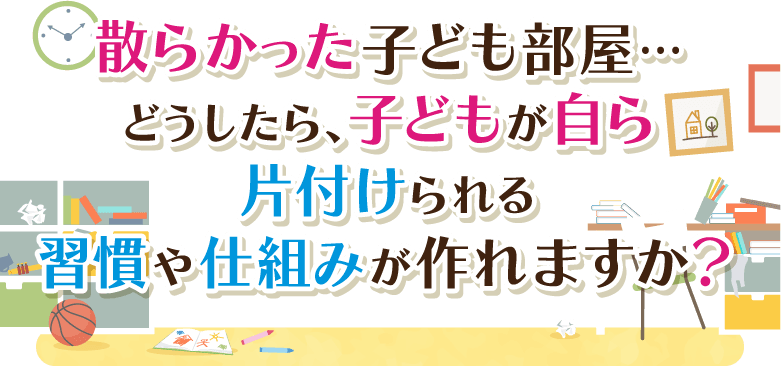









おうちデトックス代表
整理収納アドバイザー
おもちゃに洋服、学用品など、子どもの持ちモノはとても短いスパンで変化していきます。ある程度散らかるのは仕方ないことでもありますが、定期的に持ちモノを見直したり、シンプルなアクションで片付けられる仕組みを作るなど、親子で繰り返し確認することで片付ける力を付けていきましょう。
また、夏休みなどの長期休みを利用して子ども部屋の片付けに取り組むなら、長期休みに入る少し前からスタートするのがおすすめです。それはお休み前に子どもが学校からたくさんの学用品を持ち帰るから。道具箱やプリントなどモノが一気に増える前に、それらをしまうスペースを親子で作ることから始めてみてはいかがでしょうか。

おうちデトックス代表
整理収納アドバイザー
子ども部屋が片付かない原因を探り
キレイを保つ仕組みづくりを!

❶ 子ども部屋が散らかる原因は?
大人でも子どもでも、お部屋が散らかる原因は大きく分けて以下の2つです。

●モノの量が多すぎて収納スペースが足りない
●使った後に出しっぱなし
⇒まずはお子さまをよく観察し、親子で話し合い、どちらが原因なのか、はたまた両方なのかなど傾向を知ることが大切です。

❷ モノの量が多すぎるときの対策
収納スペースいっぱいにモノを入れると、出したモノを戻すことが難しく、お部屋が散らかりやすくなります。
●余白を持って収納できる量に調節することが大切
●定期的に持ちモノを見直して減らす時間を作る
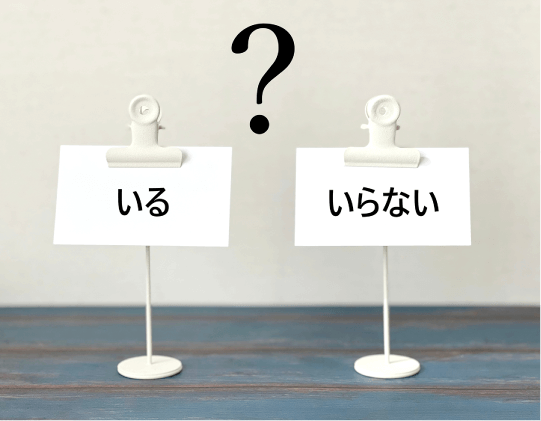
⇒サイズアウトした洋服は捨てる、最近遊んでいないおもちゃは捨てるなど、モノを処分する基準を明確化することも重要です。モノの量が多すぎる原因は、「減らす基準がわからないから後回しにしてしまう」という気持ちが強くあります。低学年までは親が基準を決め、ある程度の年齢になったらお子さま自身で決められるよう練習しましょう。処分する基準はすぐには身に付かないので、時間をかけてじっくりと。たとえば「古いモノとお別れ(捨てる)しないと、新しいモノは入ってこない」ということをお子さまに繰り返し伝えていくことが大切です。
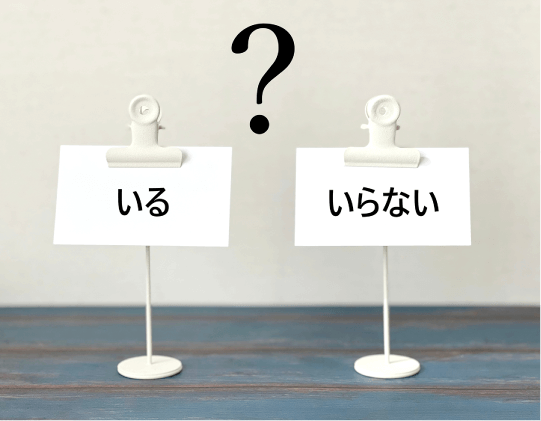
処分の仕方が迷いがちなモノ
●子どもの作品や思い出の品
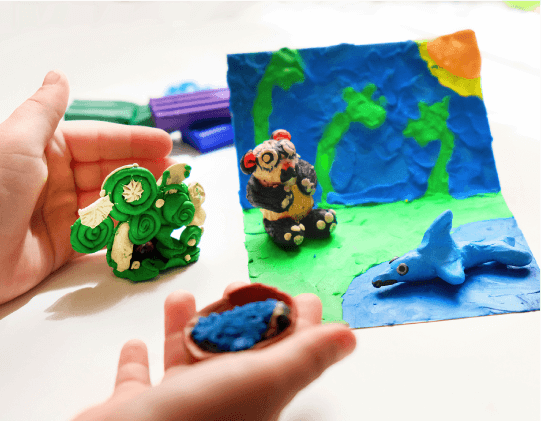
捨て難いのが工作の作品などの思い出の品です。
飾るスペースを決めて一定期間しっかり家族で楽しみ、よく褒めてあげましょう。飾った作品を毎日見たり、家族から褒めてもらったりすることで子どもは満足した気持ちになります。満足した気持ちになると、意外とすんなり処分できたりするものです。こうして新しい作品が増えてスペースがいっぱいになってきたら、親子で相談しながらどれを残すか処分するかを決めていきます。お子さまの思い出のために写真を撮っておくのもおすすめです。
●プリント
多くのご家庭でお悩みのタネになっているのがプリント類。
特に長い休みは宿題やお知らせなど、大量のプリント類が家にあふれてしまいがちです。つい後回しにしがちなプリントの片付けは、お休みに入ったらすぐ取り掛かりましょう。お知らせプリントから先に済ませ、宿題プリントやテストは、簡単なものはその場で復習したり確認して処分しても良いでしょう。プリント類は学期ごとに見直すだけでも量を減らすことができます。
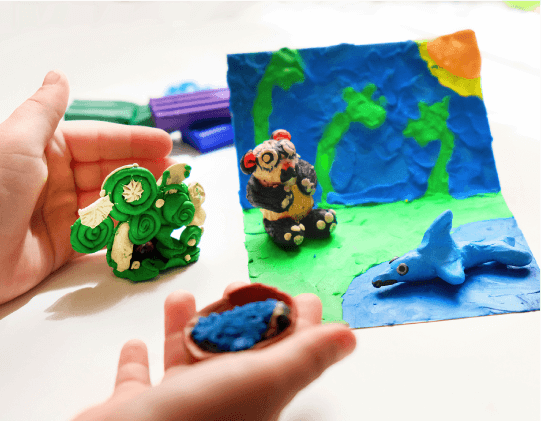
❸ 出したモノを
元に戻せないときの対策
使ったモノを元の場所にしまえないことも、お部屋が散らかる原因です。
遊ぶモノ、勉強のモノ、学校のモノ、習い事のモノなど、持ちモノをシーン別に分け、それぞれの「定位置」を決めてあげることが大切です。シーン別に分けておくことで、子どもにどのシーンで使うモノかを覚えさせる効果もあり、忘れモノや探しモノを減らすことができます。
片付けやすい定位置を作るためには、「ぽいっと置くだけ」「フックにかけるだけ」など、しまうときのアクションがなるべくシンプルになるように工夫しましょう。
●定位置を大きくラベリング

それぞれのモノの定位置には、モノの名前や絵を書いた紙などを貼り、ラベリングするのがおすすめ。これは「探すため」ではなく「戻すため」。つまり、郵便配達の際の表札と同じ役割ですね。
ブロックのおもちゃなど、箱に入れて収納するモノはその箱を置く床に、箱に近いサイズのラベルを貼っておくのもおすすめです。視覚的にラベリングされていると、ほかのモノが置かれにくくなるという効果もあります。
●見える収納でわかりやすく
おもちゃや小モノはクリアボックスやメッシュの袋など、中身が見える収納方法を使うのもおすすめです。


子どものモチベーションアップ
小学校中高学年ともなると、片付けるようにいってもなかなか聞いてくれなくなる…というのも多くのご家庭共通のお悩みです。ガミガミいいすぎると逆効果の場合も…。
片付けの時間を決めて、その間はパパ・ママも別の場所を片付けたり、「○○時までによろしくね!」と期限を決めたりするなど、ご家庭に合ったやり方をしていきましょう。次に子どものモチベーションアップのための方法をご紹介します!
面倒なこと+楽しいことをセットに

やることの後回し癖は、散らかることにつながります。そこで、やることと楽しいことをセットにして片付ける仕組みを作りましょう。たとえば、“帰ったら手洗いをした後におやつを食べる”、という流れを、“おやつを食べる前にカバンからプリントを出して親に渡すモノボックスに入れる”、までをセットにします。おやつを食べる(楽しいこと)への前段階にプリントをボックスに入れる(面倒なこと)をやることで、思っていたよりも短時間で簡単にできることに気が付き、後回し癖を減らしていくことが期待できます。

共有スペースの家事を一緒に

朝ご飯を一緒に作ったり、テーブルの上を片付けたり、子ども部屋以外の家事を一緒に行なうことで、家庭や生活に対する関心や知識を育てましょう。
おうちのどこに何があるのか、自然と身に付いてくるので、モノを定位置に戻す練習にもなります。普段は時間がなかなか取れないので、夏休みなどの長期休みを利用するのがおすすめです。

自分だけのテリトリー

子どもに「自分だけのテリトリー」を作ってあげることが大切です。子ども部屋を持たずリビング学習をしているお子さまの場合、ボックスか引き出しひとつでも構いません。テリトリーの中を自分で片付けさせると、子どもは「自分のエリア」を意識して、片付けるモチベーションが上がります。最初のうちは、親が子どもに「使ったらここに戻してね」といってあげるのもいいですね。自分の責任で管理するスペースを持つことで、“空間に合わせてモノを減らすこと”、“使ったモノを元に戻すこと”を学ぶことができます。




片付け上手なご家庭は、必ずモノの入口と出口を考えています。たとえば買う時(入口)に「置く場所があるのか」「これが本当に必要か」「代用できないなら今あるモノをどうするか、買い替えなら古いモノをどうするか」を親子で一緒に考えてから買うようにしています。処分すること(出口)を買う前に考えておくことがポイントです。散らかったら片付けることよりも、“いらないモノは捨てる”、“不要なモノは買わない”ことで片付ける習慣が自然と身に付いていっているように思います。とはいえ、片付けや買う買わないの判断を数か月だけやったくらいでは、なかなか身に付きません。小さな頃から繰り返し、ずっとやり続けて、ようやくできるようになっていきます。「大きくなってしまってもう親のいうことを聞いてくれない」とあきらめずに、今からでもいい続けてみてくださいね。
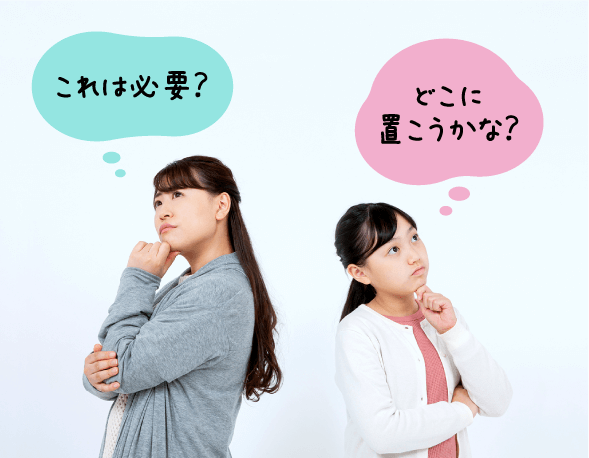

たとえば同じご家庭のきょうだいであっても、ブロックを色分けすると片付けやすい子と、まとめて箱に放り込むほうがいい子と、違いが出たりすることがあります。
全員にとっての正解はないので、お子さまの自主性を尊重しつつ親子でモノの量や収納の仕組みの見直しを繰り返し繰り返し行なっていくことが必要です。お子さま自身が選んだり片付けたりできるよう、日々の生活の中で短い時間で良いのでやっていきましょう。目先の結果だけでなく、将来、お子さまが片付けで困ることのないよう、力を付けてあげるための工夫が大切だと感じています。



整理整頓が
節約につながる!? 部屋の掃除をすると運気が上がってお金が入りやすくなるという話を聞いたことはありませんか?掃除と運気はスピリチュアル感がありますが、掃除することで部屋が整理整頓できて結果的にお金が貯まる、増える理由があります。
●整理整頓することで何がどこにあるか把握しやすくなり、同じものを購入することがなくなり、無駄遣いをしなくなる
●片付けることで必要なモノだけが残り、大切に使う習慣が身に付くため、購入の頻度が減り、節約につながる
●整理整頓の習慣が身に付くと環境をより良くしようと努力するようになり、その意識が仕事の効率化や家計管理にも反映され、収入アップや節約に結びつく
●部屋がリラックスできる空間になり、自宅で過ごす時間が増えるため、レジャー代や外食費などが減る
部屋を整理整頓してきれいな状態を維持できれば、結果として無駄遣いが減り節約につながるかもしれませんね。
そして、今までとは違ったことにお金が使え、自分のやりたかったことができ、運気が上がる。お片付けは継続することでさまざまな効果が得られます。


大橋 わか
おうちデトックス代表
整理収納アドバイザー


個人宅と建売住宅のコーディネートを長年行なう中で、整理収納の大切さに気づき、「収納のチカラで叶えるインテリア」をコンセプトに暮らす人が幸せになれるお部屋づくりをめざしています。個人宅の整理収納を中心にフリーランスとして約7年活動後、2018年1月おうちデトックスを設立。現在、テレビ・メディア多数で活躍中です。
公式Instagramhttps://www.instagram.com/ouchi.detox


大橋 わか
おうちデトックス代表
整理収納アドバイザー


個人宅と建売住宅のコーディネートを長年行なう中で、整理収納の大切さに気づき、「収納のチカラで叶えるインテリア」をコンセプトに暮らす人が幸せになれるお部屋づくりをめざしています。個人宅の整理収納を中心にフリーランスとして約7年活動後、2018年1月おうちデトックスを設立。現在、テレビ・メディア多数で活躍中です。
公式Instagram
https://www.instagram.com/ouchi.detox